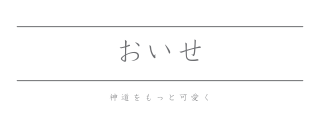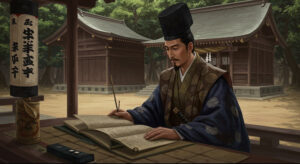みなさん、神社にお参りに行くことはありますか?おみくじを引いたり、お守りを買ったり、季節のお祭りに参加したり…。日本には約8万もの神社があるんですよ!
でも、そんな神社たちをまとめている「神社本庁」という組織があることを知っていますか?
実は戦争が終わった後の大変な時期に、神社を守るために生まれた組織なんです。
今回は、そんな神社本庁がどうやってできたのか、どんな役割を持っているのかをカンタンにご紹介します。神社の歴史と今を知れば、次のお参りがもっと楽しくなるかも♪
神社本庁って、どうしてできたの?

神社本庁は1946年2月3日に日本中の神社が集まってつくられました。
その前の年、日本は戦争に負けて、アメリカなどの国の軍隊が日本にやってきたんです。
この軍隊は「神社と国は別々にしなさい」というお達しを出しました。
そのお達しは「神道指令」というもので、1945年12月15日に出されたんですよ。
それまで神社は国と深い関係があったから、この指令でとても困っちゃったんです。
そこで、それまで神社のことを考えていた3つのグループ(皇典講究所・大日本神祇会・神宮奉斎会)が力を合わせて「神社本庁」というおうちをつくったんですよ♪
神社の昔ばなし~歴史ってステキ~

神社は日本中にたくさんあって(約8万もあるんだって!)、神様をおまつりする大切な場所なんです。
神社本庁のルールにも「みんなが良い人になれるように教えること」が目的って書いてあるんですよ。
神社の歴史はとってもふるくて、大化元年(645年)には蘇我石川麻呂という人が「お祭りと政治は一緒」という考えを広めました。
その後、大宝律令という法律ができて、神社のことがきちんと決められるようになったんです。
むかし、日本の法律では神社は国の大切な場所とされていて、みんなの心のよりどころだったんですよ!
戦争の前には、伊勢神宮を一番上にして、官国幣社や府県社、郷社、村社というように、かわいいランク分けされた神社があったんです。
神社のことを管理する「神祇院」という役所もあって、神社を大切にしていたんですよ。
戦争が終わってからの神社
戦争が終わったとき、アメリカの軍隊は「神社と国はもう一緒にしちゃダメ」って言いました。
そのせいで神社はとっても困っちゃったんです。
神祇院という役所もなくなってしまい、神社はどうしたらいいのか分からなくなっちゃいました。
3つのグループがなんとかしようと何度も話し合って、「神社本庁」をつくって、日本中の神社みんなで助け合うことにしたんですよ!
神社本庁ができた理由は、神社のステキなところを守って、みんなに神社の大切さを教えるためなんです。
神社本庁は「世界中の人が仲良く平和に暮らせますように」ってお祈りするって約束もしたんですよ。
江戸時代の終わりごろから明治時代の始まりの前には「教派神道」という新しい神道のグループもできました。
でも神社の人たちは「私たちは昔からの正しいやり方で神様をおまつりしているよ」と言って、「神社神道」と呼んだんです。
神社本庁は「神社神道」という日本の伝統を守る大切な役割をしているんですよ♡
まとめ

神社本庁は戦争が終わったあとの大変な時に、神社を守るためにできました。
日本中の神社が集まってつくった神社本庁は、神社の伝統を守って、みんなに神社の大切さを教える役割をしています。
神社本庁は「みんなが仲良く暮らせますように」というお願いも大切にしているんですよ。
昔からのやり方を大事にしながらも、今の時代に合わせて神社を守っていくのが神社本庁のお仕事なんです。
神社本庁があるおかげで、今も日本の大切な文化である神社が守られているんですね。
日本の神社は季節のお祭りやお参りができる楽しい場所で、みんなの願いごとを神様に届けてくれる大切な場所なんですよ♪