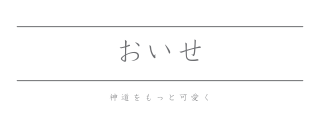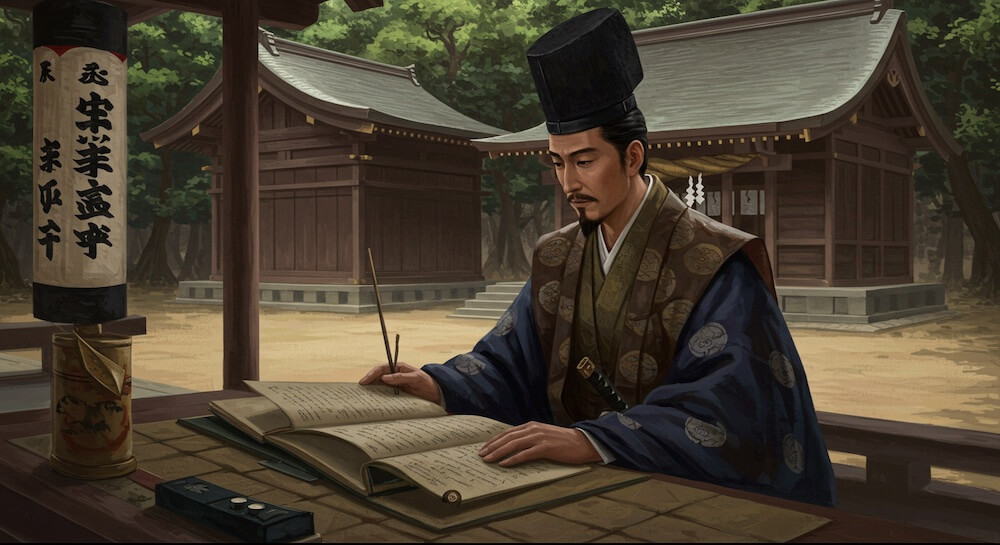-

【兵庫】みのりを祝う、旬をかこむ~ ファーマーズマーケット 6/28
直会(なおらい)とは、神事のあと神様と共に食をいただく古来の習わし。この“直会市”は、自然の恵みに感謝し、農と祈りをつなぐ、新しいかたちのファーマーズマーケットです。当日は11:00〜本殿にて神事があります🌾✨ ⬛︎農CamatoQuwa@camatoquwa_farm草... -

日本の祝詞に学ぶ心の美学|「掛けまくも畏し」に込められた敬虔な精神とは?
日本の伝統儀式において読み上げられる「祝詞(のりと)」は、単なる宗教的文言ではありません。古代から続くこの言葉の儀式には、日本人の自然観や神への畏敬、そして生命への深いまなざしが込められています。この記事では、特に時代祭祝詞や安産祈願祝... -

三社託宣とは?三大神社の神々からのメッセージと日本人の信仰心
三社託宣(さんしゃたくせん)は、中世から近世にかけて日本で広く信仰された神々からのお告げです。 伊勢神宮の天照皇大神宮、宇佐八幡宮の八幡大菩薩、春日大社の春日大明神という三つの重要な神様からのメッセージとされ、掛け軸などに記されて広まりま... -

吉田神道って何?神仏儒道を融合した中世の最強宗教を解説
吉田神道は室町時代に大きな影響力を持った神道の一派です。 「唯一神道」「宗源神道」とも呼ばれ、京都の吉田神社を拠点に発展しました。 神道に仏教や儒教、道教の要素を上手に取り入れ、明治時代まで日本の神社界に強い影響を与えていた注目の宗教思想... -

両部神道って何?仏教と神道が出会った不思議な世界をわかりやすく解説
両部神道は、日本の仏教と神道が融合した独特の信仰体系です。 真言密教の教えをベースに、仏様と神様をつなげて考える面白い世界観なんです。 この記事では、両部神道の成り立ちや特徴、そして実際の神社での事例について、歴史的な背景も含めてわかりや... -

伊勢神道って何?中世日本の神秘的な信仰をわかりやすく解説♪
伊勢神道は、平安時代の終わりから鎌倉時代にかけて生まれた神道の一つの流れです。 主に伊勢神宮の外宮の神職だった度会(わたらい)氏によって作られた神道の考え方なんです。 この記事では、日本の歴史に大きな影響を与えた伊勢神道の成り立ちや特徴に... -

伊勢神宮とは?パワースポット好き必見!神々が宿る日本最高の聖地
伊勢神宮は日本を代表する神社で、神社本庁の中心的な存在です。 五十鈴川(いすずがわ)のほとりにある内宮(ないくう)と山田原にある外宮(げくう)を中心とした神社グループです。 古くから皇室と深いつながりがあり、パワースポットとしても大人気! ... -

神籬と磐境って何?古代日本人が作った神さまのおもてなし空間
神籬(ひもろぎ)と磐境(いわさか)は、日本の神道に古くからある祭りのための場所です。 神さまをお迎えして祀るための特別な空間を作り出す役割があります。 一時的に設けられるこれらの依代(よりしろ)は、日本ならではの信仰のかたちを今に伝える大... -

「琴・書・和歌」が必須だった!? 平安時代の超エリート女性教育の秘密
平安時代の貴族社会では、高貴な女性にどのような教養が求められていたのでしょうか。 村上天皇の時代に仕えた宣耀殿の女御芳子は、小一条左大臣の娘として生まれ、父から特別な教育を受けました。「書道」「琴の演奏」「古今和歌集の暗誦」—これらは平安... -

菅原道真が詠んだ秋の絶景:「このたびはぬさ」の歌に込められた美と敬意
菅原道真といえば「東風吹かば」の梅の歌をイメージする方が多いかもしれませんが、実は秋の紅葉を美しく詠んだ和歌も残しているんです!今回は古今集に収められた一首を紹介します。 急な旅で神様への捧げ物を用意できなかった道真が、目の前に広がる紅葉...