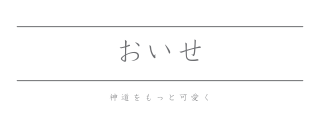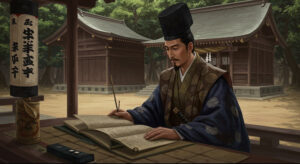三社託宣(さんしゃたくせん)は、中世から近世にかけて日本で広く信仰された神々からのお告げです。
伊勢神宮の天照皇大神宮、宇佐八幡宮の八幡大菩薩、春日大社の春日大明神という三つの重要な神様からのメッセージとされ、掛け軸などに記されて広まりました。
この記事では、三社託宣の内容や歴史的背景、そして日本人の信仰生活に与えた影響について詳しく解説します。
三社託宣の内容と特徴
三社託宣は、中央に天照皇大神宮、右側に八幡大菩薩、左側に春日大明神の神号とそれぞれのお告げの言葉が記されています。
多くの場合、これらの神様の図像も一緒に描かれています。
お告げの言葉は漢文体で書かれており、「正直」「清浄」「慈悲」といった道徳的な教えが強調されているのが特徴です。
これらは神仏習合の考え方を反映しており、それぞれのお告げは各神様の徳を表しています。
たとえば天照大神は「正直」、八幡大菩薩は「慈悲」、春日大明神は「清浄」という徳目と結びつけられることが多いです。
三社託宣の起源と伝播
三社託宣は平安時代以前の史書や記録には見られません。
その起源については、正応年間(1288-1293年)に東大寺東南院の聖珍親王の時に池の水面に三社の託宣が示現したという説があります。
また、応永年間(1394-1428年)の『醍醐枝葉抄』が最初のまとまった記述とされています。
このことから、南都(奈良)の僧侶や醍醐寺系の僧侶、両部神道の関係者が三社託宣の成立に影響を与えたと考えられています。
しかし、三社託宣が広く普及したのは吉田神道の影響が大きいといわれています。
吉田兼倶(よしだかねとも)は『神楽岡縁起』(別名「三社託宣本縁」)で吉田斎場の由来とともに三社託宣を解説し、吉田神道の教えに取り入れました。
さらに皇室の依頼により、斎場で天皇直筆の三社託宣を供養する儀式も行われました。
これにより、公家から武家へと信仰が広がり、託宣和歌など分かりやすい解説書を通じて一般の人々にも普及していったのです。
三社託宣の信憑性と社会的影響
時代が下るにつれて、三社託宣が吉田家に下されたという起源説も登場しましたが、考証家の間では託宣の信憑性が疑問視されるようになりました。
江戸時代の学者・伊勢貞丈は、吉田兼倶が自分の家の利益のために偽作したと断じています。
それでも託宣の内容自体は道徳的な教えとしての効果を持ち、庶民の道徳教育の手段として広く受け入れられました。
通俗神道家や石門心学者、三教一致(神道・儒教・仏教の調和)を支持する仏教関係者にも支持され、多くの解説書や掛け軸、印刷物が庶民向けに作られました。
各地では三社への燈籠を奉納する講が結成され、三社託宣への信仰は全国的に広まりました。
この信仰は江戸時代を通じて衰えることはなく、日本人の宗教観や道徳観に大きな影響を与え続けました。
まとめ
三社託宣は、日本の三大神社の神々からのお告げとして広く信仰された教えです。
その内容は正直、清浄、慈悲といった道徳的な教えを中心としており、神仏習合の思想を反映しています。
起源については諸説ありますが、吉田神道の影響で広く普及し、公家から武家、そして一般庶民にまで広まりました。
学者の間では偽作説もありましたが、その道徳的な教えは人々に受け入れられ、江戸時代を通じて日本人の精神生活に深く浸透しました。
三社託宣は、複数の宗教思想が融合した日本独自の信仰文化を象徴する興味深い事例といえるでしょう。