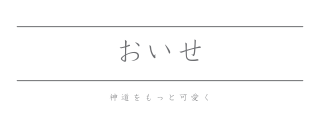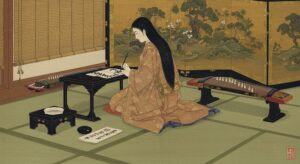菅原道真といえば「東風吹かば」の梅の歌をイメージする方が多いかもしれませんが、実は秋の紅葉を美しく詠んだ和歌も残しているんです!今回は古今集に収められた一首を紹介します。
急な旅で神様への捧げ物を用意できなかった道真が、目の前に広がる紅葉を「錦」に見立てて神様に捧げるという素敵な発想。天才と称えられた道真の機知に触れながら、和歌の美しさや背景にある歴史をわかりやすく解説していきます。秋の風情と共にお楽しみください。
秋の紅葉を詠んだこの和歌もまた、彼の優れた表現力が光る逸品です。古今集の羈旅部(旅の歌の部)に収められた一首を見てみましょう。
現代語で理解する道真の心
このたびはぬさもとりあへず手向山紅葉の錦神のまにまに
この歌を現代語に訳すと次のようになります:
「今回の旅は急なことで、道中の道祖神に捧げる御幣(ごへい)の用意もできませんでした。この錦のように美しい手向山の紅葉を、どうぞ神様のお心のままにお受け取りください。」
歌の背景:宇多上皇との御幸
宇多上皇は道真公の才能を評価し、右大臣にまで取り立てた人物でした。この歌が詠まれた御幸(みゆき:天皇の外出)は、道真以外にも多くの歌人が供をした盛大なものだったと伝えられています。
旅の安全祈願と美しい代替品
昔の人々は旅に出る際、神様への捧げ物として「御幣(ごへい)」を持参し、道中の道祖神(どうそじん)にお供えして旅の安全を祈願していました。
この歌では、道真が御幣の代わりに目の前に広がる見事な紅葉を神様への捧げ物としています。準備ができなかった御幣の代わりに、自然が生み出した美しい紅葉の錦を捧げるという発想に、道真の機知と表現力が感じられます。
菅原道真と秋の詩歌
菅原道真というと「東風吹かば匂いおこせよ梅の花」のような梅の歌で知られていますが、実は秋を詠んだ素晴らしい作品も多く残しています。この和歌のほかにも「秋思詩」や「九月十日」など、秋の風情を巧みに表現した作品があります。
紅葉を錦に見立てる表現技法
この歌では「紅葉の錦」という表現が使われています。これは「見立て」という和歌の表現技法で、美しい紅葉を高価な織物である錦に例えています。この比喩によって、紅葉の鮮やかさや価値の高さを強調しているのです。
語句の解説
- このたびは:「たび」は「度」に「旅」を響かせる言葉遊びになっています
- ぬさ:木綿や錦の切れ端で作られた神への捧げ物
- とりあへず:「とる」は捧げる意味、「〜あふ+打消」は〜しきれないの意
- 手向山:「手向け(供えること)」をする山の意味で、固有名詞ではない
- 紅葉の錦:紅葉の美しさを着物の錦織に見立てた表現
- 神のまにまに:神の思うままに、という意味
今日に息づく和歌の心
この和歌は、急な旅で準備が整わなかったという窮状を、目の前の美しい紅葉を神への供物に見立てることで詠嘆に変えた秀作です。自然の美しさへの感動と神への敬意が見事に表現されています。
秋のえも言われぬ美しい景色を頂いた、そんな自然への返礼として雅楽を捧げる—そんな情景が浮かぶような一首です。山の神様のために特別に整えた舞台で、雅楽を奉納する舞人たち。秋の日差しをスポットライトのように浴びながら、心を込めて舞う姿が目に浮かびます。
菅原道真の才能と感性は、この一首からも十分に伝わってくるでしょう。現代を生きる私たちも、季節の美しさに心を寄せ、感謝する心を持ちたいものですね。
まとめ
菅原道真の「このたびはぬさもとりあへず」の和歌は、窮地を創造性で乗り切る素晴らしい例といえるでしょう。急な旅で神様への捧げ物を準備できなかったという困った状況を、目の前の美しい紅葉を「錦」として捧げるという発想で詠み上げた感性の豊かさには驚かされます。
梅の歌のイメージが強い道真ですが、秋の風景を詠んだ作品も数多く残しており、四季折々の日本の自然を愛した彼の幅広い感性がうかがえます。「見立て」という和歌の表現技法も巧みに使いこなし、紅葉と錦を重ねることで視覚的な鮮やかさを表現しています。
古典和歌は難しいイメージがありますが、このように現代語訳や背景を知ることで、千年以上前の人々の感性や知恵に触れることができます。秋の紅葉を見るとき、ふと道真の和歌を思い出してみてはいかがでしょうか?自然の美しさへの感謝と敬意の気持ちが、今も昔も変わらない日本人の心として息づいているのかもしれませんね。