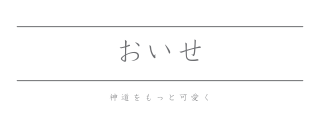神社のお祭り、参加したことありますか?神輿を担いだり、屋台で食べ歩いたり、楽しい思い出がたくさんあるかもしれませんね♪
実は神社のお祭り(神社祭祀)には、地域のみんなが幸せになるための深い意味が込められているんです。
今回は、神社祭祀がもつ公共的な意味や、私たちの生活との関わりについてわかりやすくご紹介します。お祭りの見方が変わるかもしれませんよ!
神社祭祀とは~古代からつながる日本の心~

神社祭祀の公共性を考えることは、はるか昔の日本のルーツをたどり、国の基礎を確かめる行為といえます。
神社には特別な由緒あるお祭りがたくさんあります。
例祭(れいさい)、祈年祭(きねんさい)、新嘗祭(にいなめさい)、式年祭(しきねんさい)、鎮座祭(ちんざさい)などの特別なお祭りから、歳旦祭(さいたんさい)や元始祭(げんしさい)といった年中行事まで、さまざまな祭祀が執り行われています。
神社祭祀の本質~感謝と尊敬の心~
お祭りで大切にすべきは精神です。
その根本は「報本反始(ほうほんはんし)」という感謝の心に尽きます。
報本反始とは、遠く神武天皇の時代にさかのぼり、皇室のご先祖様である神様に感謝を捧げた「天神郊祀(てんしんこうし)」の精神なんです。
神様の恵みに感謝して神様の徳を讃え、神様の意志に従って国民の生活に活かしていくことが大切なんですよ。
したがって神社のお祭りは、国や地域の公共の祭りとして行われながら、みんなが神様の意志を尊重し、日々の生活に活かしていくことを目指しているんです。
神社祭祀の歴史的意義~日本書紀に記された神の言葉~
『日本書紀』の神代巻によると、天孫降臨(てんそんこうりん・神様の子孫が天から地上に降りてくること)の際に、高皇産霊尊(たかみむすびのみこと)という神様が次のようにおっしゃいました。
「私は天の神籬(ひもろぎ)と天の磐境(いわさか)を立て、私の孫のために祀りを行おう。天児屋命(あめのこやねのみこと)と太玉命(ふとだまのみこと)よ、天の神籬を持って葦原中国(あしはらのなかつくに・日本のこと)に降り、また孫のために祀りを行いなさい」
この神様の言葉が、神社祭祀の国家的な意味を確立したものと考えられています。
「私の孫のために」という言葉は、天皇をはじめとする国民全体のために祈り続けることを意味し、お祭りを行う目的がはっきりと示されているんです。
戦前、神社は国家・公共のものであり、そこで行われるお祭りも公共的な意味を持っていました。
法律が変わっても、神社祭祀の本質は変わらないものなんですよ。
神社と地域のつながり~ハレとケの世界~
神社を中心とする神道の特徴は、神社と氏子(うじこ・その神社を信仰する地域の人々)の一体感にあります。
それは日常生活の延長線上にあるお祭りのあり方にも関係しています。
神社だけが神聖な場所ではなく、普段の「ケ」という日常が、「ハレ」という特別な時間に変わることができる「お祭りの論理」が大切なんです。
昔からあった村社会が昭和30年代に大きく変わり、田舎でさえも都会化してきた「都市型社会」では、物があふれてハレが日常化しています。
しかし文明の普遍性ではなく、文化の個別性には民族性や土地・生活が土台となっているんですよ。
祭りが作る地域の絆~現代社会でも大切な役割~
神道は懐かしさを感じる故郷の宗教です。
地域・文化・風土と離れて神道は存在できず、各地の風土に根ざした人間づくりをお祭りの根幹としてきました。
年に一度、地域が一つになれるお祭りに社会秩序の回復を促し、共同意識を取り戻すことに真の生命力があるんです。
不変の意識がお祭りの周期性によって守られてきました。
神聖な時間と空間を作り出し、あるいは共同体意識を回復するため、「故郷の宗教」と言うべき神道では、風土に根ざした人づくりを中心に据えてきたんです。
神様をお祭りする精神を中核として、豊かな伝統文化のある土地を背景に、先祖から子孫へのつながりを重視した社会づくりが大切なんですよ。
まとめ

神社祭祀は単なる楽しいイベントではなく、地域の人々の幸せを願い、神様に感謝する深い意味を持っています。
古代から続く「報本反始」の精神は、神様への感謝と尊敬の心を表すもので、現代社会でも大切な価値観です。
お祭りを通じて地域の絆を深め、先祖から子孫へとつながる社会づくりに貢献しているのが神社祭祀の役割なんです。
次にお祭りに参加するときは、ただ楽しむだけでなく、そこに込められた意味にも目を向けてみてくださいね♡