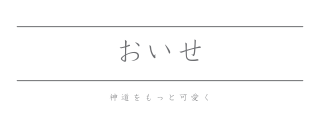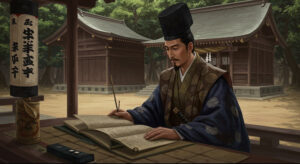両部神道は、日本の仏教と神道が融合した独特の信仰体系です。
真言密教の教えをベースに、仏様と神様をつなげて考える面白い世界観なんです。
この記事では、両部神道の成り立ちや特徴、そして実際の神社での事例について、歴史的な背景も含めてわかりやすく解説します。
日本ならではの宗教観を知るきっかけになるはずですよ。
両部神道の基本
両部神道とは?その成り立ち
両部神道は真言密教から生まれた神道の一種です。
真言密教では金剛界曼荼羅と胎蔵界曼荼羅という、宇宙の成り立ちを図で表した「曼荼羅」を信仰の中心に置いています。
この両方の曼荼羅に描かれている仏様に、日本の神様を当てはめて考える真言宗の神道を「両部神道」と呼んでいます。
「両部神道」という名前が初めて登場したのは、吉田兼倶(よしだかねとも)という神道家が1500年頃に書いた「唯一神道名法要集」という書物が最初だとされています。
つまり「両部神道」という考え方は、1500年前後に生まれた比較的新しいものなのです。
この時代は室町時代後期にあたり、日本の宗教文化が複雑に入り混じっていた時期でもありました。
曼荼羅と神様の関係性
真言密教の曼荼羅は、仏様の世界を表した宇宙図のようなものです。
金剛界曼荼羅は智慧の世界を、胎蔵界曼荼羅は慈悲の世界を表しているとされています。
両部神道では、これらの曼荼羅に描かれた仏様と日本の神様を結びつけて、「神様の本当の姿は仏様だ」という考え方を広めました。
当時の人々にとって、神様と仏様は対立するものではなく、同じ存在の違う側面として理解されていたのです。
名草神社の事例
名草神社と妙見宮の混乱
名草神社には「天御中主神を祀るために両部神道を構成し、社名を名草神社から妙見宮に改めた」という説明があります。
この説明では、天御中主神と妙見大菩薩を結びつけていますが、本来の主祭神である名草彦命との関係については触れていません。
なぜなら「名草彦命」と「妙見大菩薩」は全く関係がないことが理解されていたからです。
実はこの説明こそが、「妙見宮」と「名草神社」が別物であることを示す重要な手がかりなのです。
天御中主神は日本神話に登場する最初の神様で、妙見大菩薩は北極星を神格化した仏教の存在です。
この全く異なる二つの存在を結びつけようとするところに、明治時代の神道政策の影響が見て取れます。
キーワードは天御中主神
名草神社の説明で注目すべきは「天御中主神」というキーワードです。
近年まで天御中主神についての歴史的研究が十分ではなかったことが、混乱の一因かもしれません。
天御中主神は『古事記』に登場する最初の神様ですが、実は古代の神社ではあまり祀られておらず、中世以降に重要視されるようになった神様なのです。
このような歴史的背景を知らずに神仏習合の説明を行うと、どうしても矛盾が生じてしまいます。
両部神道で説明する限界
但馬妙見信仰と両部神道
但馬の妙見信仰は元々仏教に基づくものでした。
これを「両部神道」という概念で説明すると、さまざまな矛盾が生じてしまいます。
まず、但馬の妙見日光院は「両部神道」という言葉が生まれるずっと何百年も前から「妙見社」と呼ばれていました。
山名宗全という武将が戦勝祈願した妙見社の時代は、両部神道の概念が生まれる前の歴史なので、当時はまだ石原地区に妙見社(日光院)があり、現在の名草神社の場所には妙見様はまだ祀られていませんでした。
つまり「妙見社(妙見宮)」の歴史と「名草神社」の歴史が同じであるということはあり得ないのです。
時間軸から見る矛盾
時間の流れで考えると、「両部神道によって名草神社が妙見宮になった」という説明は成り立ちません。
仮に名草神社が古くからある神社だったとしても、両部神道の概念が生まれる前から但馬には妙見信仰があり、妙見社(日光院)は存在していました。
1153年の記録には「但馬国妙見山より妙見大菩薩勧請」という記述があり、但馬の妙見信仰がいかに古くから広まっていたかを示しています。
さらに、「妙見宮」と呼ばれるようになったのも江戸時代に慈性法親王が日光院に「妙見宮」という額をご寄進されてからで、それ以降、妙見社=日光院という妙見大菩薩の霊場を「妙見宮」と呼ぶようになったのです。
日本中の「妙見宮」は同じようにお寺だったことを意味しています。
教義面での矛盾
教義の面から見ても問題があります。
実は金剛界曼荼羅と胎蔵界曼荼羅には、妙見大菩薩は描かれていないのです。
真言宗の教えでは、天御中主神(または名草彦命)と妙見大菩薩が同じ存在であるという考え方はありません。
これは「両部神道」という言葉を便利に使っているだけで、実際の信仰の歴史や内容を正確に反映していないことを示しています。
明治時代の神道政策の影響
神仏分離と強制的な変化
これらの説明の背景には、明治維新後の神道国教化政策があります。
明治政府は神仏分離令を出し、それまで神仏習合で成り立っていた多くの寺社を強制的に分離しました。
多くの仏教施設が廃止されたり、神社に改変されたりする中で、但馬の妙見信仰も大きな影響を受けたのです。
このような政治的な宗教政策によって、長い歴史を持つ地域の信仰が無理やり変更されたことで、どうしても説明に矛盾が生じてしまうのです。
歴史の書き換え
神社の解説に「山名宗全をはじめ、武将が戦勝祈願をした」などと記載されているのは、元々お寺だった日光院の歴史をそのまま取り込んだものです。
これは本来別々だった施設の歴史を混同させる結果になっています。
明治以前の「名草神社」の歴史が「名草神社」として存在せず、また「妙見宮」と呼ばれるようになったのも江戸時代中期からなのです。
こうした歴史的事実を無視して作られた説明は、時間軸で考察しただけでもさまざまな矛盾を含んでいます。
まとめ
両部神道は1500年頃に生まれた概念で、真言密教の曼荼羅と日本の神様を結びつける試みでした。
しかし、但馬の妙見信仰のような古くからある仏教的信仰を両部神道の枠組みで説明しようとすると、時間軸や教義の面で多くの矛盾が生じてしまいます。
両部神道という概念だけでは説明できない信仰の形があることを理解するのが大切です。
名草神社と妙見宮の事例は、明治時代の神道国教化政策が地域の信仰にどのような影響を与えたかを示す興味深い例といえるでしょう。
日本の信仰の歴史は、想像以上に複雑で奥深いものなのです。
古い文献や史料を丁寧に読み解きながら、本来の信仰の姿を探ることが、日本の宗教文化を正しく理解する第一歩になります。
遠い昔の人々がどのような思いで神や仏を信じ、祈りを捧げてきたのか、その心に思いを馳せてみると、現代の私たちの生活にも新たな発見があるかもしれませんね。