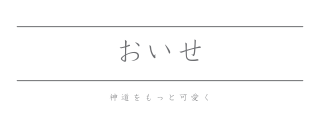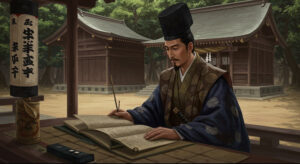伊勢神道は、平安時代の終わりから鎌倉時代にかけて生まれた神道の一つの流れです。
主に伊勢神宮の外宮の神職だった度会(わたらい)氏によって作られた神道の考え方なんです。
この記事では、日本の歴史に大きな影響を与えた伊勢神道の成り立ちや特徴について、わかりやすくご紹介します。
伊勢神道の誕生と発展
伊勢神道は平安時代の終わりから鎌倉時代にかけて、伊勢神宮の外宮で神職を務めていた度会氏の間で生まれました。
鎌倉時代の中期から後期にかけて、度会行忠(わたらいゆきただ)を中心に発展していきます。
特に元寇(げんこう)という蒙古からの侵略があった時期に、日本が一致団結する動きの中で大きく広がりました。
その後、度会常昌(わたらいつねまさ)がこの考え方を引き継ぎ、南北朝時代の吉野で度会家行(わたらいいえゆき)によって完成されたとされています。
伊勢神道は後の時代に生まれた吉田神道などの考え方にも大きな影響を与え、日本の神道の歴史の中でとても重要な位置を占めているのです。
伊勢神道が生まれた背景
日本では平安時代に「神仏習合」という考え方が広まりました。
これは神様と仏様は実は一体だという考え方です。
奈良時代になると、神社の中に「神宮寺」という寺が建てられるようになりました。
神様のために僧侶が置かれ、神様の前でお経を読んだり、神様に菩薩の称号を贈ったりして、だんだん仏教が優位な立場になっていきました。
そんな流れの中で「本地垂迹説(ほんじすいじゃくせつ)」という考え方が登場します。
これは「神様の本当の姿は仏様や菩薩で、日本の人々を救うために神様の姿で現れた」という考え方です。
伊勢神道はこの考え方とは逆に「神本仏従(しんぽんぶつじゅう)」という、神様を中心に考える思想が見られるんです。
この考え方の背景には、高僧たちが神道に関心を持つようになったこと、伊勢神宮の経済が不安定だったこと、外国からの危機に対して「神の国・日本」という意識が高まったことなどがあります。
伊勢神道の特徴と評価
伊勢神道は「度会神道」や「外宮神道」とも呼ばれ、同じ頃に生まれた「両部神道」と並んで、神道思想の先駆けとなりました。
特に伝統的な神様を中心に考える立場だったため、その後の神道思想に大きな影響を与えました。
しかし江戸時代に入ると、儒学が思想界の主導権を握るようになります。
儒学には強い反仏教的な考えがあったため、神仏習合の要素を持つ中世神道は否定されてしまいます。
また古典研究が発達したことで、古人の名前を借りて書かれた中世の神道書は「偽書」として批判されました。
江戸時代後期には国学が盛んになり、国学者たちは外来思想が伝わる前の古代を理想と考えていました。
そのため儒教や仏教と混ざり合った中世神道の考え方は、「古来の神道の教えをゆがめるもの」として否定されたのです。
伊勢神道への批判点
江戸時代の伊勢神道批判は主に次の3つにまとめられます:
- 伊勢神道の書物が古人の名前を借りた偽書であり、信じるに値しない
- 外宮の祭神を国常立尊(くにとこたちのみこと)と説くなど、古典に基づく正しい伝承を勝手に変えている
- 仏教や儒教、道教などの考え方を無理に取り入れている
明治以降の神道研究も国学者の研究を基礎として始まったため、このような江戸時代の国学的な伊勢神道観の影響を受けています。
まとめ
伊勢神道は平安時代末期から鎌倉時代にかけて、伊勢神宮の外宮神職である度会氏によって生み出された神道思想です。
神様を中心に考える「神本仏従」の立場から、その後の日本の神道思想に大きな影響を与えました。
江戸時代には儒学者や国学者から批判されましたが、日本の宗教思想の歴史を理解する上でとても重要な存在です。
伊勢神道について知ることで、日本人の信仰のルーツや歴史的な宗教観の変遷についても理解が深まりますよ。