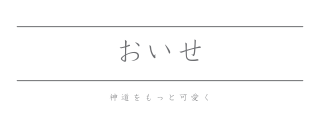伊勢神宮は日本を代表する神社で、神社本庁の中心的な存在です。
五十鈴川(いすずがわ)のほとりにある内宮(ないくう)と山田原にある外宮(げくう)を中心とした神社グループです。
古くから皇室と深いつながりがあり、パワースポットとしても大人気!
この記事では伊勢神宮の成り立ちや歴史、見どころをわかりやすく解説しますね。
伊勢神宮って何?基本情報を解説
伊勢神宮は三重県伊勢市にある、日本で最も重要な神社のひとつです。
神社本庁のトップに位置する存在で、多くの参拝客が毎年訪れます。
伊勢神宮は実は「内宮」と「外宮」という2つの主要な神社と、それに関連するたくさんの別宮や摂社などからなる神社グループの総称なんです!
内宮は正式には「皇大神宮(こうたいじんぐう)」、外宮は「豊受大神宮(とようけだいじんぐう)」と呼ばれています。
内宮の始まり~天照大神と八咫鏡のストーリー
内宮がどうやって始まったのか、その由来はとても神秘的です。
天照大神(あまてらすおおみかみ)から天孫ニニギノミコトに授けられた八咫鏡(やたのかがみ)という神聖な鏡があります。
崇神天皇(すじんてんのう)の時代、この鏡の神聖さに畏れを感じた人々は倭(やまと)の笠縫村(かさぬいむら)に移しました。
その後、垂仁天皇(すいにんてんのう)の時代に、皇女である倭姫命(やまとひめのみこと)がこの鏡を持って旅に出ます。
彼女は「大神様が住むにふさわしい場所」を探して各地を回り、最終的に伊勢にたどり着きました。
五十鈴川の上流で神様からのお告げを受け、そこに鏡を安置したのが内宮の始まりとされています。
外宮はどうやってできたの?
外宮には別の歴史があります。
もともと豊受大神(とようけのおおかみ)は丹波の国(現在の京都府北部)に祀られていました。
雄略天皇(ゆうりゃくてんのう)の時代、「食物を司る神様を近くに呼びたい」という神様のお告げがあり、伊勢に移されたと言われています。
この豊受大神は「御饌都神(みけつかみ)」といって、食べ物や食事を管理する神様で、内宮の天照大神に食物を供える大切な役割を担っていたんです!
インスタ映えする美しい建物も必見ですね。
伊勢神宮はどうやって今の形になったの?
最初の伊勢神宮は「神籬(ひもろぎ)」という、木や枝を使った簡素な祭祀場でした。
本格的な建物ができたのは天武天皇の時代(673年~674年)といわれています。
その後、持統天皇が伊勢に行幸した692年には社殿が完成していたようです。
伊勢神宮の最大の特徴は「式年遷宮(しきねんせんぐう)」という、20年ごとに社殿を建て替える伝統があること。
この伝統により、古代からの建築様式や技術が今日まで守られているんです。
まとめ
伊勢神宮は日本の神道信仰の中心として、1300年以上もの間、大切に守られてきた特別な場所です。
内宮と外宮の2つの主要な神宮を中心に、多くの関連施設がある複合的なパワースポットといえます。
その起源は神話の時代にまでさかのぼり、皇室との深いつながりの中で発展してきました。
20年ごとの式年遷宮によって守り継がれている伊勢神宮は、日本の伝統文化や歴史を感じられる最高のスポットです!
伊勢神宮を訪れるなら、内宮と外宮の両方を参拝するのがおすすめ。
食べ歩きも楽しい「おかげ横丁」や「おはらい町」も合わせて訪れてみてくださいね♪