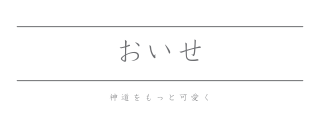平安時代の貴族社会では、高貴な女性にどのような教養が求められていたのでしょうか。
村上天皇の時代に仕えた宣耀殿の女御芳子は、小一条左大臣の娘として生まれ、父から特別な教育を受けました。「書道」「琴の演奏」「古今和歌集の暗誦」—これらは平安時代の理想的な女性教養とされていました。
本記事では、古典に残された一節から、当時の貴族社会における女性教育の理想像と、文学作品に見られる敬語表現の特徴について探ります。平安時代の雅な世界への旅にお連れします。
原文
村上の御時に、宣耀殿の女御と聞えけるは、小一条の左の大臣殿の御女におはしけると、誰かは知りたてまつらざらん。まだ姫君と聞えける時、父大臣の教へきこえたまひけることは、『一つには御手を習ひたまへ。次には、琴の御琴を、人より異に弾きまさらんとおぼせ。さては古今の歌二十巻をみなうかべさせたまふを、御学問にはせさせたまへ』となん聞えたまひける、ときこしめしおきて、御物忌なりける日、古今をもて渡らせたまひて、御几帳をひき隔てさせたまひければ、女御、例ならずあやし、とおぼしけるに、草子をひろげさせたまひて、
本文
村上天皇と宣耀殿の女御
原文では次のように記されています。
村上の御時に、宣耀殿の女御と聞えけるは、小一条の左の大臣殿の御女におはしけると、誰かは知りたてまつらざらん。
これは「村上天皇の御代に、宣耀殿の女御として知られていた方は、小一条の左大臣の娘であったということを、誰が知らないでしょうか」という意味です。
この宣耀殿の女御芳子は、平安時代中期の貴族社会で重要な位置を占めていました。小一条左大臣という高位の貴族を父に持ち、後に村上天皇の女御となる彼女は、生まれながらにして恵まれた環境にありました。
理想の女性教育
まだ姫君と呼ばれていた若い頃、父である大臣は彼女にこのような教えを授けました。
まだ姫君と聞えける時、父大臣の教へきこえたまひけることは、『一つには御手を習ひたまへ。次には、琴の御琴を、人より異に弾きまさらんとおぼせ。さては古今の歌二十巻をみなうかべさせたまふを、御学問にはせさせたまへ』となん聞えたまひける
これは「まだ姫君と呼ばれていた若い頃、父大臣が教えたことは、『一つには書道(御手)の稽古をしなさい。次に、琴を人よりも優れて弾けるように心がけなさい。そして古今和歌集二十巻をすべて暗記することを、あなたの学問としなさい』と言われたそうです」という意味です。
この教えは、平安時代の貴族社会における理想的な女性教養の三要素を示しています:
- 書道(御手) – 美しい筆跡は教養の証であり、手紙のやり取りが重要だった平安社会では特に重視されました
- 琴の演奏 – 音楽の才能は感性の豊かさを示し、宮中での交流においても重要でした
- 古今和歌集の暗誦 – 905年に編纂された最初の勅撰和歌集を暗記することで、和歌の教養を身につけることができました
これらの教養は単なる嗜みではなく、宮中で生きていくための実践的なスキルでもありました。特に和歌の知識は、会話や文通において欠かせないものだったのです。
敬語表現から見る人間関係
この短い一節の中にも、平安時代の複雑な敬語表現が見られます。
- 「聞え」 – 宣耀殿の女御芳子に対する謙譲語
- 「たまひ」 – 小一条左大臣に対する尊敬語
- 「おぼせ」 – 宣耀殿の女御芳子に対する尊敬語
- 「きこしめし」 – 村上天皇に対する尊敬語
- 「させたまひ」 – 宣耀殿の女御芳子に対する尊敬語
これらの敬語表現から、登場人物間の身分関係や物語の語り手の視点を読み取ることができます。村上天皇に対しては最高レベルの敬語が使用され、宣耀殿の女御と小一条左大臣に対しても、それぞれの地位に応じた敬意が表されています。
宮中生活の一場面
物語はさらに続きます。
ときこしめしおきて、御物忌なりける日、古今をもて渡らせたまひて、御几帳をひき隔てさせたまひければ、女御、例ならずあやし、とおぼしけるに、草子をひろげさせたまひて、
これは「天皇がその言葉を心に留めておいて、天皇が物忌みの日に古今和歌集を持ってこさせ、几帳(きちょう:屏風のような室内の仕切り)を引いて隔てたところ、女御は普段と違う様子に不思議に思いました。そして草子(本)を広げさせた」という意味です。
この場面からは、宮中における日常の一コマと、和歌集が実際にどのように用いられていたかを垣間見ることができます。
まとめ
平安時代の女性教育は、現代とは大きく異なりながらも、その時代の社会で生きるために必要な教養を身につけるという点では共通しています。書道、琴、和歌という三つの教養は、感性を磨き、コミュニケーション能力を高め、文化的背景を共有するための重要な手段でした。
また、この短い一節に見られる複雑な敬語表現は、平安文学の特徴であるとともに、当時の厳格な身分社会を反映しています。現代の私たちがこうした古典を読むことで、遠い時代の人々の生活や価値観に触れ、日本文化の奥深さを再発見することができるのです。
宣耀殿の女御の物語は、平安貴族の華やかな世界だけでなく、その裏にある教育の重要性と、文化継承の姿を今に伝えています。私たちも現代において、何を学び、何を次世代に伝えるべきか、考えるきっかけとなるでしょう。