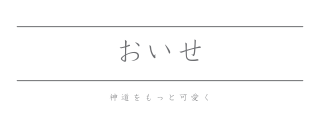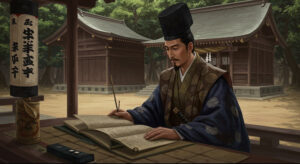古事記に登場する有名な物語の中から、今回は「黄泉の国(よみのくに)」と「天岩戸(あまのいわと)」の神話についてご紹介します!
愛する妻を追って死者の国へ旅立ったイザナギの悲しい冒険と、弟の行動に怒って洞窟に引きこもってしまった太陽神・天照大御神の物語。現代のドラマよりも面白く、ラブストーリーよりも切ない古事記の世界。日本文化の源流となったこれらの神話を、今回はわかりやすく解説していきます!
古代の物語から学べる現代にも通じる教訓とは?神話の世界へ一緒に旅立ちましょう!
イザナギの黄泉の国訪問~愛する人を取り戻す旅~
愛する妻を失ったイザナギ
イザナギ(伊邪那岐命)は、愛する妻のイザナミ(伊邪那美命)が亡くなってしまい、とても悲しみました。
彼女に会いたい一心で、死者の国である「黄泉の国」まで妻を探しに行くことを決意したのです。
これって、愛する人のためなら死後の世界にまで行く覚悟があるという、究極のラブストーリーの始まりなんです!
黄泉の国での再会
長い道のりを経て、ついにイザナギは黄泉の国でイザナミと再会します。
「一緒に地上へ戻ろう」と説得するイザナギに対し、イザナミは「もう遅いの…黄泉の国の食べ物を食べてしまったから戻れないの」と答えました。
それでも諦めきれないイザナミは「黄泉の神と交渉してくるから、ちょっと待っていて」と言い残しました。
約束破りと恐怖の逃走
しかし、待ちきれなくなったイザナギは、イザナミの姿を見に行ってしまいます。
そこで目にしたのは…変わり果てたイザナミの姿でした。
その恐ろしい光景に驚いたイザナギは、恐怖のあまり逃げ出してしまいました。
怒ったイザナミは「恥をかかせた!」と黄泉の国の神々を遣わしてイザナギを追いかけます。
現世と黄泉の国の境界線
必死に逃げるイザナギは、最終的に黄泉比良坂(よもつひらさか)という現世と黄泉の国の境界まで辿り着きます。
そこで大きな岩で道を塞ぎ、イザナミとの関係を断ち切りました。
このシーンは別れの悲しさと同時に、死者と生者の世界は交わってはいけないという戒めが込められているのかもしれませんね。
神々の誕生~禊(みそぎ)から生まれた三貴子~
穢れを落とす禊(みそぎ)
黄泉の国から無事に戻ったイザナギですが、死の世界の穢れが体についていました。
そこで筑紫の日向(現在の宮崎県あたり)の橘の小門のアハキ原で禊を行うことにしました。
禊とは体を清める儀式のことで、今でも神社で手や口を清める「手水(ちょうず)」の原型とも言えるんですよ。
三貴子の誕生
イザナギが身を清めていく過程で、様々な神々が誕生します。
特に重要なのが、イザナギが左目を洗った時に生まれた「天照大御神(あまてらすおおみかみ)」です。
彼女は太陽の女神として、後に日本の最も重要な神となります。
続いて右目からは月の神「月読命(つくよみのみこと)」、そして鼻を洗った時には「建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)」が誕生しました。
この三柱を「三貴子(みはしらのうずのみこ)」と呼びます。
天岩戸事件~世界が闇に包まれた日~
スサノオの乱暴な行為
スサノオ(建速須佐之男命)は姉である天照大御神に会いたいと天上界にやってきました。
しかし天照大御神は弟の乱暴な性格を警戒します。
スサノオは自分が悪意を持っていないことを証明するため誓約を行いますが、その後も問題行動を続けてしまいました。
天照大御神の田畑を荒らしたり、聖なる馬を機織り小屋に投げ込んだりして、ついには天照大御神の侍女を死なせてしまいます。
天照大御神の引きこもり
スサノオの行為に怒り悲しんだ天照大御神は、天の岩屋という洞窟に隠れてしまいました。
太陽の神である天照大御神が姿を隠したため、世界は闇に包まれ、作物が育たなくなって神々や人々は困り果てました。
これって現代で言えば、家族との喧嘩で部屋に引きこもってしまった状態みたいなものかも…?
神々の作戦会議
困った八百万(やおよろず)の神々は天照大御神を洞窟から出すための作戦会議を開きます。
長い話し合いの末、様々な準備を整えました。
- 鏡を作って岩屋の前に置く
- 賑やかな宴会を開く
- アメノウズメに踊りを踊ってもらう
天照大御神の復活
天宇受賣命(あめのうずめのみこと)が陽気に踊りだし、その様子を見た神々が大笑いしました。
「なぜそんなに笑っているの?」と不思議に思った天照大御神が岩屋の外を覗くと…
岩屋の前に置かれた鏡に映った自分自身の姿が目に入ります。
その隙に力持ちの天手力男命(あめのたぢからおのみこと)が岩屋の戸を開け、天照大御神を外に引っ張り出しました。
こうして世界に再び光が戻り、秩序が回復したのでした。
神話から学ぶこと~現代に通じるメッセージ~
黄泉の国の物語から
イザナギとイザナミの物語からは、「約束を守ることの大切さ」や「生と死の境界線を尊重すること」を学べます。
どんなに愛する人でも、死者と生者の世界は別だということを受け入れる必要があるのかもしれません。
ちなみに「黄泉の国の食べ物を食べたら戻れない」というのは、ギリシャ神話の「ペルセポネーの物語」にも似た要素があり、世界共通のモチーフなんですよ!
天岩戸の物語から
天岩戸の物語からは、「太陽と光が生命や秩序の象徴である」という教えを読み取れます。
また、問題解決のために神々がそれぞれの得意分野を活かして協力する姿は、チームワークの大切さも教えてくれています。
天照大御神を岩屋から出すために知恵を絞り、みんなで協力して危機を乗り越える姿は、現代社会でも通じる「団結の力」を示しているのではないでしょうか。
まとめ
古事記に描かれた「黄泉の国」と「天岩戸」の物語は、単なる神話ではなく、人間の感情や社会の秩序について深いメッセージを含んでいます。
悲しみや怒り、好奇心や恐怖など、現代人と変わらない感情を持った神々の物語は、何千年経った今でも私たちの心に響くものがありますね。
日本文化の基盤となったこれらの神話をもっと身近に感じて、古事記の世界を楽しんでみてください♡