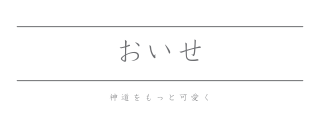一時的に設けられるこれらの依代(よりしろ)は、日本ならではの信仰のeかたちを今に伝える大切な文化です。
この記事では、神籬と磐境の歴史や作り方、意味などをわかりやすくご紹介しますね。
神籬(ひもろぎ)とは
神籬(ひもろぎ)は一時的に設けられる祭りの場所で、神さまをお迎えするための依代(よりしろ)のひとつです。
特に樹木や枝を使ったものをヒモロキと呼んでいます。
「ヒ」は霊的な力を、「モロ」は「モリ(森)」の古い形を表すとされています。
「キ」については木や城を意味するといわれていますが、はっきりとした説は定まっていません。
現代では青竹や榊を四すみに立て、しめ縄を四角く張りめぐらせるのが一般的です。
中央には榊を立てて、幣(ぬさ)をつけて神さまの依り代として祀ります。
神籬という言葉は『日本書紀』の天の孫が降りてきた話に登場します。
天からの神籬が記されているほか、崇神天皇の時代に笠縫村に磯堅城神籬を建てて天照大神をお祀りしたことなども書かれています。
さらに、天日槍が持ってきた出石の宝物の中に熊神籬があったという記録も残っています。
磐境(いわさか)とは
磐境(いわさか)は、昔の人々が神さまをお迎えして祭るために石を使って作った場所のことです。
神籬と同じように『日本書紀』の天孫降臨の話に、神籬と一緒に磐境ができたと書かれています。
本当に石を使ったのかについてはいろいろな説があり、長い間はっきりしない施設と考えられていました。
でも伊勢神宮の中にある滝祭神の石積み祠や奈良県の多武峰村のお祭りの仮宮、考古学の発見から、小さな石で作られた一時的な祭壇だったとわかってきました。
神籬や榊と一緒に使われることが多く、形は四角や丸い形で、土を盛り上げたような形をしています。
真ん中に大きめの石を置くこともあるようです。
祭りの場所を神聖にするために、昔の人たちはこうした工夫をしていたのですね。
まとめ
神籬と磐境は昔の日本のお祭りでとても大事な役割を果たしてきた神聖な場所です。
神籬は主に木や枝を使った神さまの依り代で、磐境は石を使ったお祭り場です。
どちらも『日本書紀』という古い書物に書かれていて、昔から日本人の信仰生活に深く根付いてきました。
今でも神社のお祭りや地域の伝統行事の中に、その名残を見つけることができます。
これらのお祭りの場所は、自然と仲良く暮らし、自然の中に神さまを見つけてきた日本人の心を表す象徴といえるでしょう。
私たちのご先祖が大切にしてきたこのユニークな信仰のかたちを知ることで、日本文化の奥深さに触れるきっかけになりますよ。